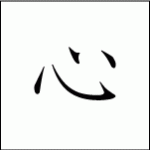伝えたいことを分析する
伝えたいことを書く。 これは当然のことで、文章の基本ですね。 書き手自身が、伝えたいことがわかってなければ伝えることはできません。 これもまた、当然のことです。 しかし、この部分がおろそかになっては ...
見出し作りの考え方
見出しに使う文言は、書き手の悩みどころですね。 今回は、本文で使われている言葉から作り出す方法をご紹介します。 完成までは、たった3ステップです。 さまざまな作り方がある中でも、もっともかんたんな方法です。 ...
「説明」の基本的な考え方
どのような文章でも、説明をしなければならない局面を迎えます。 このときわかりやすく説明できるどうかは、書き手の手腕にかかっているといえるでしょう。 今回は、説明の基本的な考え方に焦点をしぼってご紹介します。 ...
表現のインフレは文章を乱す
文章を書くときには、いつも冷静であるべきです。 さまざまな思いが心の中にあったとしても、それをそのまま表現すると文章が乱れてしまうからです。 具体例を交えながら考えていきましょう。 原 ...
自分にしか書けないことを見つける
ありきたりな内容を並べるだけでは、価値のある文章を書くことはできないでしょう。 自分にしか書けないことがあれば、たとえ秀逸な書き方でなくても、その文章は特別なものになります。 「自分にしか書けない内容」と銘打てば、難しく考えて ...
同音異義語に注意する
同じ発音で違った意味をもつ言葉を、同音異義語といいます。 日本語には、挙げればきりがないほど、数多くの同音異義語が存在します。 言葉を扱う書き手としては、注意が必要です。 原文 彼は、私の意見に意義 ...
聞きかじりの言葉に注意する
言葉の意味は、正確に覚える必要があります。 どこかで聞いた表現を、あいまいな解釈をしたままの状態で使ってはいけません。 自分のボキャブラリーについて、過信や油断があると、次のようなミスが起こってしまうかもしれません。 ...
お役所言葉を避ける
お役所言葉とは、役所や省庁、行政機関で使われる独特の言い回しのことです。 公的な書類をみると、難しい表現で書かれていることがありますね。 あのような表現は、自分の文章に持ちこまないようにしましょう。 ...
なじみのある表現を使う
理解できない言葉が文章のなかにあったとき、読み手はどのような行動をとるのでしょう。 言葉の雰囲気からなんとなく予想してくれれば、まだ救いはあります。 最悪の場合、その部分を読み飛ばしてしまうことも十分に考えられま ...
無駄な修飾語を省く
文章を読むという行為は、ただでさえエネルギーを使うものです。 無駄な表現が書かれた文章は、読みたくないものですね。 特に、過度な修飾をしてしまうと、かえって読み手に負担をかけてしまいます。 今回は、「無駄な修飾語を省く」をテー ...