書き出しから「説明するクセ」をつけない
前提として理解しておきましょう。
読み手は、何万文字もかけた説明を望んではいません。
したがって、小説を執筆するときには、説明要素が含まれる文章を排除していくべきです。
ここでいう「説明」とは、読み手に知っておいてほしい情報を提示する書き方を指します。
「今は何年何月で、ここは何県何市で、これは誰々で、こういう状況で……」
といったように、土台を作るように前置きしてしまうのです。
この書き方は、「論文」のような説明要素の強い文書には必要不可欠でしょう。
しかし、これを小説に持ちこむ必要はありません。
小説では本来、こうした情報を作品の要素として扱います。
描写しながら伝えたり、登場人物の会話や語り手の言葉の中で匂わせたりして、それとなく伝えるのが定石です。
試行錯誤しながら必要な情報を組み込んでいく作業は、執筆の醍醐味でもあるのです。
つまり、説明という書き方は、その機会を失ってしまうことと同じなのです。
小説というフォーマットで勝負する以上は、説明ばかりの平面的な書き方ではなく、奥行きのある立体的な書き方を目指すべきです。
実力を発揮できない状態の土台を、自分で固めてはならないのです。
ここで、かんたんな解決策をご紹介します。
説明ではなく、「場面」から入るようにすればいいのです。
具体的な手法としては、書き出しに会話をもってくること。
執筆において内容をとくに説明しがちなのは、冒頭の書き出し部分です。
会話から物語を始めることで、場面から入らざるを得ない状況を自分から作り出すことができるのです。
手垢にまみれた手法ではありますが、効果的であることは間違いありません。
「説明」によって、物語の進行に必要な情報をすべて読み手に伝えてしまえば、書き手としては楽なのでしょう。
しかしここまでご紹介したとおり、それは悪手である確率が非常に高いのです。
作品の魅力を十分に伝えるためにも、説明するクセをつけないように意識しましょう。

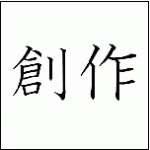

ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません