読み手と作品の距離【作品に導く】【対話する】
読み手は最初、そっぽを向いています。
読み手がこちらを向いたとき、書き手はその後のことを考えなければなりません。
ここで考えるべきは、「読み手と作品の距離」です。
「書き手と作品の距離」はなるべく離れるよう心がけることが重要でした。
しかし「読み手と作品の距離」は、できる限り近づけるように努力すべきです。
読み手と作品の距離
小説の冒頭を読んで、「おもしろそうだ」と思ったらそのまま読み進めるはずです。
つまらなそうだったり、好みに合わなかったりすれば、そっとページを閉じてしまう人もいるでしょう。
作品に目を通し始めた段階の読み手は、まだまだ遠いところにいるのです。
だからこそ書き手は”良い作品”を書くために、読み手を作品に惹きつけたり、引き込んだりするような工夫を考えるわけですね。
工夫の仕方はさまざまですが、目的は「読み手と作品の距離」を縮めることです。
たとえば「空の青さ」を描くとしましょう。
書き手が意図をもって、方向性を示しながらその様子を文章に落とし込んでいくはずです。
描いた「空の青さ」とまったく同じものを読み手が共有したとき、両者の距離は”ゼロ”に縮まったといえるでしょう。
書き手の役目は「導く」こと
もちろん実際には、距離が”ゼロ”になる状態を目指す必要はありません。
縮めるべきは「読み手と作品の距離」であり、書き手と読み手の距離ではないのです。
読み手には読み手なりの「空の青さ」があり、書き手はその振り幅を尊重するべきです。
読み手と一緒になって、空を見上げる様子をイメージしましょう。
重要なのは、書き手が読み手に対して「ほら見て、あの空」と言えるまで距離を縮めることです。
もしも読み手が遠くにいれば声をかけることはできないはずで、書き手が縮めるべき距離はここにあります。
そこで見た「青さ」が小説そのもので、書き手の役割は読み手の目線を作品に導くことなのです。
対話を大事にする
「読む」という行為が起こったとき、そこには文章を媒介したコミュニケーションが発生します。
いわば「書き手と読み手の対話」が始まるわけですね。
前項にあった例が「ほら見て、あの空」ではなく、「さっさと上見ろよ、ボケカス」だったとします。
これでは、せっかく声が届くまで距離を縮めたのに、その努力が台無しになってしまいますね。
だからこそ書き手は、文章を通じて行われる読み手との対話を大事にしていかなければならないのです。
もちろんこれは、作品が仕上がってしまったときに心がけても意味がありません。
書いている最中から、常に読み手のことを考えるべきです。
「読み手はどのように感じるのだろう」
「この文章からなにを思うのだろう」
「その目にはどう映るのだろう」
読み手に伝えるための工夫であり、対話を成立させるための配慮でもありますね。
この姿勢が、読み手と作品の距離を縮めることにつながります。
「書き手」と「読み手」、そして「作品」の関係性を考えながら執筆しましょう。
■ 参考


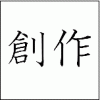

ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません