抽象的な概念を書かない【誘惑に勝つ】【書き手は型枠を整える】
小説と向き合うとき、書き手はなにかしらの意図をもって書くはずです。
「○○を伝えたい」や「□□を描きたい」や「△△をわかってもらいたい」といったことですね、
書き手は抽象的な概念を織り込みながら、物語を仕上げていくわけです。
しかし「作品に織り込む」といっても、「文章として書くかどうか」はまた別に考えるべき問題です。
「言語化された概念」が感性を鈍らせる
冒頭であった”概念的なもの”は、「テーマ」「モチーフ」「思想」といいかえることもできます。
作品全体に共鳴する大きなものから、場面の細部に落とし込む小さなものまでを、書き手は扱うわけです。
とはいえ書き手は、あいまいなものを「言語化して書く」ことに慎重になるべきです。
なぜなら概念を言語化する作業は、読み手にとっては説明でしかないからです。
たとえば「旅先で出会った見知らぬ人との一幕」から、”出会いの大切さ”を描くとしましょう。
二度と会うことのないであろう人とのやりとりによって、書き手はさまざまなことを読み手に伝えます。
しかし書き手が地の文で「やはり出会いは大切だと思った」と書けば、それで済まされてしまう内容です。
概念を言語化して書いてしまうと、本来は多様であるべき「読み手の感性」を鈍らせることになるのです。
「型枠を整える」イメージで
子どものころの「砂場遊び」を思い出しましょう。
お城・車・動物などの「型枠」を使いながら、さまざまなものを造形しました。
この感覚は、小説の書き方に転用できます。
小説を書くとき、書き手は型枠を整えるイメージをもつことが重要です。
それがプラスチック製の型なのか、金属性の型なのか、はたまた手作業で整えるのかは問いません。
出来上がったとき、読み手が「そう見える」ように造形することが大事です。
かたちが崩れそうだからといって、「出会いは大切だ」と書いてしまわないように注意しましょう。
「言語化の誘惑」に勝つ
書き手は、物語にもっとも近い距離で接する存在です。
頭のなかには、クリティカルに伝えられる言葉が浮かんでくるでしょう。
「これは○○だった」
「それは□□でしかない」
「あれは△△という意味で……」
ついつい書きたくなる「言語化の誘惑」に、書き手は勝たなければなりません。
「概念的な要素」を言語化して説明したくなるのは、型枠が整っていないからです。
本来、作品に描かれたものを感じるのは読み手の特権であって、書き手が奪ってはいけないものです。
書き手がなにかを描くときは、言語化に頼らず、型枠をしっかり整えることに注力するべきです。
型枠さえしっかり整っていれば、読み手はその造形を感じとることができるでしょう。
■ 参考


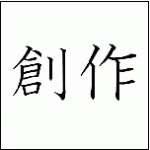


ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません