「おもしろい文章」を書くために
今回は、「おもしろい」の意味について考えましょう。
ご存知のとおり、「おもしろい」にはいろいろな意味があります。
書き手が「おもしろい文章」を考えるときには、この意味を巧く扱おうと努力するはずです。
しかし、本質は意外にもシンプルです。
「おもしろい」の語源から考えてみると、書き手のやるべきことが見えてきます。
いろいろな「おもしろい」がある
英語におきかえるとわかりやすいでしょう。
次に挙げる単語は、すべて「おもしろい」と訳すことができます。
例
● interesting (興味深い)
● funny (可笑しい)
● amusing (楽しい)
場合によっては “good”(良い)や”cool”(かっこいい)、”amaizing”(おどろくべき)で「おもしろい」と表現することもあります。
ひとつの傾向として、英語ではそのときの状況にあわせた単語をあてはめながら、その感情を伝えます。
日本語では、すべて「おもしろい」の一言で完結できてしまいます。
話者からすれば便利に思えますが、書き手として表現するとなれば事情が変わってきます。
「文章のおもしろさ」を考えたときに、その概念があまりにも漠然としているのです。
そうなると書き手は、何をどうすべきかがわからなくなってしまいます。
さらには、「おもしろい」という言葉だけでは細かなニュアンスを使い分けることができません。
概念としても、実用面においても、扱いが難しいのです。
「おもしろい(面白い)」の語源
日本語の「おもしろい」は、書き手にとって不便に思えるかもしれません。
しかし、本当はとても便利な言葉です。
「おもしろい(面白い)」の語源には、すべての感動に共通する意味が込められているからです。
昔の日本では、夜になると囲炉裏に集まってさまざまな話をしていたそうです。
「興味を引くような話」を誰かがすると、火を囲んでいた皆が「ハッ」と顔を上げます。
すると、囲炉裏の火に照らされた”顔面が白く”光ったように見えたのです。
諸説あるものの、これが「面白い」の語源だと主張する人がいます。
この説が本当であるかどうかは、あまり関係ありません。
語源となった(と思われる)情景から、書き手のやるべきことが見えてきます。
読み手を「ハッ」とさせよう!
読み手が顔を上げ、面(おも)が白くなるような文章。
「えっ!?」「本当に!?」「そうなの!?」
「すごい!」「なるほど!」「たしかに!!」
読み手が顔を上げるそのリアクションをもたらせることが、「おもしろい文章」には必要です。
書き手は「おもしろい文章」を考えるときに、読み手が「ハッ」とする様子を見据えましょう。
読み手が目を見開いてしまうようなコンテンツを盛り込むことができれば、それはおもしろい文章になっているはずです。
■ 参考




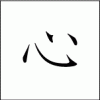

ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません