構造の「揺らぎ」から変化をもたらす
今回は、次の内容を発展させます。
ここでの「変化」とは、抽象的であり、上位概念に近いものでもあります。
書き手がこれを意識するときは、テーマの設定から考えがちです。
しかしテーマの設定ではあまりにも漠然としていて、読み手の心を動かすような変化を作ることは難しいでしょう。
この変化に対して、書き手自身が抽象的に考える必要はありません。
物語の構造から手がけることができます。
たとえば、物語を進めるにあたって、書き手は次のように “配役” するとします。
● 主人公(被害者)
● 主人公の母(加害者)
⇒ 主人公は、自分を邪険にする母のことを疎ましく思っている。この関係性のなかで起きる事件や、主人公の心情を描く。
小説は「ネガティブなものを受け入れる器」をもっているため、それを活用しようとするパターンですね。
ありきたりな配役であり、典型的な構造ともいえますが、これ自体に問題はありません。
問題なのは、両者の関係性が “平行線のまま物語が終わる”ことです。
物語の最後まで、主人公は悶々としたままでいて、その母は主人公に対してなんらかの攻撃を続ける。
現実にはこの関係性がまったく変化しないのは不自然です。
読み終えるまでそのドロドロとした関係が続いていれば、ただ鬱屈したままの物語でしかなく、「読み手に何かを残すこと」が難しくなってしまいます。
仮に、このような展開を作ればどうでしょうか。
● 我慢の限界を迎えた主人公は、母との離別を決意する
● 母には、主人公をぞんざいに扱う真っ当な理由があった
● 最後、主人公と母が和解する
物語のなかでいくつかの山場があれば、二人の関係に「緊張と緩和」がもたらされます。
この緊張と緩和に含まれる起伏が重要です。
これによって、読み手はさまざまなことを感じ、考えるわけです。
「なんてひどい親なんだ」
「そういう理由があったのか」
「仲直りできてよかった」
物語をダイナミックに展開させれば、それにともなって登場人物の感情も移り変わります。
つまり、構造からもたらした変化から「揺らぎ」を生じさせるわけです。
その揺らぎが作品全体に波及すると、読み手の心境も変化するのです。
私たちを取り巻く環境は、常に変化しています。
人間関係はもちろん、職場や学校、家庭の状況も同様ですね。
変化から生じた揺らぎが私たちに作用したとき、そこにはドラマがもたらされます。
この「現実世界の在り方」や「人間の在り方」を投影し、揺らぎを再現することことこそ、小説らしさを実感できる要因となるのです。
構造から組み立てただけの局所的な変化は、やがて、読み手の心に残るような包括的な変化へと広がります。
これを意識しながら書けば、作品のクオリティを向上させることにもつながるでしょう。
■ 参考


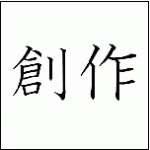

ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません