描写は「何を感じるか」で決まる
人間には、見えるはずのものを見ようとする性質があります。
たとえば「富士山」をイメージしましょう。
青みがかったゆるやかな三角形の頂点が、白く染まっている様子をイメージするはずです。
しかし、近くで見る富士山は青みがかっていないですし、山頂に雪がない時期だってあります。
これは、「富士山はそうであるはず」という思い込みからくるものです。
小説を書くとき、書き手は、このような人間の性質に逆らわなければなりません。
「草原にいる場面」を描写するとしましょう。
舞台となるのは、おそらくこのような絵だと思います。

青空の下、緑が悠然と茂る様子。
どこか馴染み深さを感じるこの画像は、おわかりのとおり、Windowsの壁紙ですね。
私たちの脳裏に刷り込まれているイメージを描くときは、注意が必要です。
「草原にいる場面」を描くとして、書き手は、この画像を模倣するだけでは不十分なのです。
もちろん、草原を画像どおりに描写することが必要な場合もあるでしょう。
しかしながら、これは見えるはずのモノでしかありません。
描写ではなく、「模写」といったほうが適切でしょう。
実際の風景には、さまざまな要素が存在します。
吹き抜ける風の感触、草や土の香り、虫の羽音、隠れるように咲く小さな花。
風景からこれだけのものが感じ取れることを、書き手は自覚しなければなりません。
見たままを模写するのではなく、書き手がそこから何を感じ取るのかが重要です。
想定していないことは感じにくいの人が多い中、書き手としての感性を光らせなければなりません。
それを描写で表現することで、読み手は実感を得られ、作品に奥行きが生まれるのです。

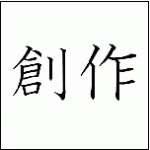

ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません