嗅覚を使う
「におい」は、脳に直接作用するといわれています。
ポイントとなるのは、においの感覚、つまり嗅覚ですね。
これをうまく小説に取り入れれば、読み手の感覚に訴えかける文章を書けるようになります。
嗅覚は、五感のなかでもより原始的な感覚なのだそうです。
たとえば、動物は、食べ物の匂いを嗅ぐことで食べられるかどうかを判断します。
人間も同様に、食べた経験のない食べ物の匂いを嗅ぐことは往々にしてあることですね。
こうした危険予知の判断に使われるほど、私たちにとっては鋭敏な感覚なのです。
トマトスープを飲んだ。
シンプルでわかりやすいのですが、具体的ではありません。
嗅覚でとらえるように書きかえてみましょう。
そのスープから放たれる完熟トマトの香りが、部屋中に広がっていた。
スプーンですくったそれを口に近づけると、バジルの香りが鼻をかすめた。
あくまで一例ではありますが、トマトスープを食べたときの様子は具体的になりました。
もちろん、完熟トマトやバジルの香りは、読み手に実感をもたらす要素として機能しています。
嗅覚の使いどころは、描写だけではりません。
嗅覚には、記憶を呼び起こす効能もあります。
思考をめぐらせるきっかけとしては、目で見たり耳で聞いたりすることのほうがわかりやすいのかもしれません。
「この街は、若い頃に訪れたことがある」
「この曲は、若い頃に聴いたことがある」
これらに比べると、嗅覚で得られるものは、とても遠回りしているように思えます。
① ある花の香りを嗅ぐ
② 幼いころの思い出がよみがえる
③ そのとき庭に咲いていた花の匂いだった
感覚としては直接的でも、順序だてて文章にするとまわりくどいですね。
しかし、このまわりくどさを利用すれば、とても便利に使うことができます。
たとえば、「A⇒B」というように場面を転換したくても、なかなか繋げられない場合。
ここに嗅覚から得られるものを取り入れれば、十分な納得感を得られます。
(場面A)交差点で立ち止まると、一瞬、花の匂いが漂った。
あの家の庭にかつて咲いていた花の匂いは、幼いころの日々を呼び起こした。
(場面B)両親が離婚したのは、僕が小学生のころだった。
このようなトリッキーな転換も、アリでしょう。
一見遠くはなれたものを、ぐっと身近に引き寄せる。
嗅覚にはこのような性質があり、これは小説の執筆においてとても有効な手段になります。
当然ながら、嗅覚は鋭敏な感覚がゆえに、乱雑に扱ってはいけません。
上記の例だって、何度も使える手ではなく、「ここぞというときの隠し玉」としてもっておくくらいの心持ちがちょうどいいですね。
嗅覚をもって読み手に伝える場合は、使いどころを吟味して、効果的に折り込みましょう。

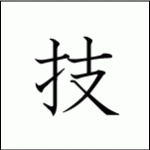
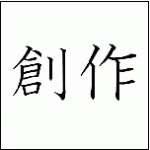

ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません