ドンデン返しを作る
今回は、「ドンデン返し」を作るときの考え方についてご紹介します。
ドンデン返しのある物語は、読み手に大きな満足感をもたらします。
しかし書き手としてこれを使いこなすには、緻密な計算が必要になります。
結論からいえば、ポイントはどのように読み手を裏切るかです。
ドンデン返しを成立させるために、まずは3つの考え方を徹底しましょう。
1つ目は、読み手の心情を見据えながら物語を書くこと。
読み手がどのような状態でいるかを見据えなければ、「何をもって意外なのか」を考えることはできません。
2つ目は、そこに生まれるであろう憶測を把握すること。
見据えた読み手の心情を具体化して、意外な展開へと持ち込むためには「読み手が何を考えているか」を把握しなければなりません。
ここは、ドンデン返しの「前フリ」を考えるときの基盤となります。
3つ目は、憶測を裏切る展開を考えること。
登場人物や物語の流れに同調していた読み手が、ここで作られた展開で裏切られるわけです。
読み手の憶測をしっかり把握した上で展開するのはもちろん、書き手の意図が悟られないよう慎重になることも大事ですね。
これら3つの考え方は、あくまでドンデン返しの下地を整えるためにあります。
実際の執筆では、読み手をどのように裏切るかがポイントになります。
方法論として考えたとき、ひとつ確実にいえるのは「読み手の疑問を解く場面」から考えたほうが構築しやすいということです。
どこかのタイミングで読み手を誤解を解く場面を作ると、そこに至るまでが読み手を騙すための機能をもちます。
● 起
⇒ 荷物を発送するために、主人公は郵便局に向かった
● 承
⇒ 受取人の喜ぶ顔が、目に浮かんだ
● 転
⇒ 自宅に忘れものをしたことに気が付き、主人公はすぐに引き返す
● 転
⇒ 妻が作った弁当は、玄関の脇にあったようだ
● 結
⇒ 遅刻しないよう、主人公は急いで郵便局に向かった
主人公は郵便局の利用者ではなく、郵便局員だったというオチです。
読み手の誤解を解く場面として、起承転結の「転」をひとつ挿入しました。
これをもとに物語を構築すると、前段の「起承転」の場面は読み手を騙すために存在することになり、だからこそ最後の「結」でストンと落とせるのです。
このように「読み手の疑問を解く場面」から考えると、構造を主体としながら物語を展開できます。
そのなかで登場人物の動きを巧みに操りながら、「前フリ」をしっかりと効かせ、外堀を埋めるように思い込ませるのです。
注意すべきポイントは、ドンデン返しの程度です。
読み手の心情や憶測をイメージする段階では、すべてが書き手の管理下にあります。
どのようにして裏切るかを考えるときに、はじめて「発想力」や「創造力」などの具体的な能動性が求められ、それを読み手に投げかけるのです。
意気込んだ書き手がすさまじい変化球を投げるのはけっこうですが、読み手がそれをキャッチできなければ意味がありませんね。
読み手が受け止められる程度を目安に、意外性のある球を投げましょう。
書き手は、読み手の予想の真逆をついても良いでしょうし、まったく別のところから違う要素をもってきてもかまいません。
読み手の心を動かすことを意識しながら、しっかりとオチにまとめることができれば、ドンデン返しは成立するはずです。
いわゆる「ミスリード」や「叙述トリック」と呼ばれる手法も、基本的な原理は同じです。
物語をおもしろくするために、読み手を裏切っていきましょう。
■ 参考


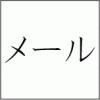
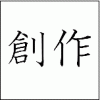

ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません