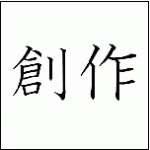【明記しない】伝えたいことを「浮き彫り」にする【読み手に預ける】
創作では、明記を避ける傾向にあります。 要するに「伝えたいことをはっきり書いてはいけない」のです。 創作の書き方におけるセオリーのようなもので、どこかで見聞きしたことのある書き手も多いでしょう。 今回はこのセオリーについて、実 ...
【一人称で書く】主人公と地の文の関係を考える【主人公の年齢】【文章の偏差値】
小説を一人称で書く場合、地の文の土台となるのは"主人公自身"です。 とくに「主人公の年齢」は内面を標榜する基準となり、地の文の書き方に強い影響を及ぼします。 そこで書き手が悩むのは、年齢に応じた地の文を書くべきかということです ...
【身体的な特徴】変わるものと変わらないもの【気をつけるべきこと】
物語を書くにあたって、「変わるもの」と「変わらないもの」があります。 書き手はこの概念をきちんと理解しつつ、しっかりと管理しながら物語を書き進めなければなりません。 今回は「身体的な特徴」を中心に考えていきます。 ...
【一人称で書く】物語として成立させる【困難な点】【解決策】
一人称であれば、原則として単独の視点で書いていくでしょう。 そうなると当然ながら、物語の世界でのインプット・アウトプットはひとつになるわけです。 視点が強く限定された一人称で、物語を成立させるのは至難の業です。 今回は「物語の ...
【一人称の小説】主人公のパーソナリティを知らしめる【外的な要因から】
小説において、主人公のパーソナリティは非常に重要です。 読み手はここに興味をもったり、心酔したりするわけで、「小説そのものの魅力」にもつながる要素といえます。 小説を一人称で書くメリットは、主人公のパーソナリティを濃密に表現す ...
【一人称の小説】視点の乱れを防ぐ【包括的なマネージメント】
書き手は「視点の乱れ」に注意しなければなりません。 小説全般にいえることではありますが、一人称で書く場合はその扱いがデリケートになります。 一人称小説での視点は、物語全体に共鳴する要素です。 これをないがしろにすることのないよ ...
【書き手と登場人物】作中で「意識」を書き分ける【使い方】
今回は、「書き手の意識」と「登場人物の意識」について考えてみましょう。 小説を書くときには、これらを意図的に操作できるようになるべきです。 ここでは両者を区別することはもちろん、具体的な使い方もふまえてご紹介します。 ...
【作品の印象】小説のタイトルについて【象徴となる言葉】
タイトルの付け方、決め方について悩んでいる書き手は多いでしょう。 これを「言葉の選び方」として考えてしまうとキリがなく、個々の作品によっても最適解は変わってきます。 この記事ではタイトルのに使う文言を具体的に考えるのではなく、 ...
【情報と説明文】詩的センスをもって読み手の心に訴えかける【感覚と描写文】
創作するときに必要な「詩的センス」について考えましょう。 とはいえ、書き手が詩を自作できるようになったり、誰かの詩を引用する方法をご紹介するわけではありません。 読み手の心に訴えかける文章を描くことにフォーカスします。 そのた ...
【小説】長編と短編について考える【書き手の目線】
小説の長編と短編について考えます。 「どこまでが短編で、どこからが長編なのか」 ここに疑問を抱えている人は多いでしょう。 今回は「書き手の目線」に重きをおいて、これを考えていきます。 長編と短編を区 ...