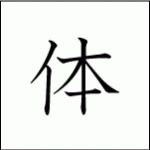【応用編】主語を明確にするための読点
こちらの記事にある内容を、さらに発展させましょう。 主語を明確にするための読点は、もっとも基本的な用法のひとつです。 しかし、甘くみてはいけません。 使い方しだいでは、文章を進化させることができるのです。 例をみ ...
読点の用法 基本の5つ
読点の用法はさまざまで、そのすべてに意味や役割があります。 ここでは、基本中の基本である5つの用法に絞ってご紹介します。 今まで、自身の感覚のみを頼りに読点を打っていた人は、この内容をもって意識づけしましょう。 ...
逆接を連続させない
逆接は、効果的に使える接続詞のひとつです。 これで文章同士をつなげば、読み手の視点を変えて文章に抑揚をつけたり、書き手の主張を強調させたりすることができるのです。 しかし逆接を近い距離で連続させると、読み手の混乱を招いてしまう ...
導入はシンプルに書く
構成において戸惑いがちなのが、導入の書き方です。 どこまでの情報を、どの程度の文字数で組み込むべきか。 書き手は、テーマや媒体にあわせてこれを考えなければなりません。 原文 バランスボールを使ってエ ...
「しかし」の効果的な使い方
「しかし」は、逆接の役割を果たす接続詞です。 誰もが当たり前のように使っていますが、これを効果的に使うとなるとコツが必要になります。 例を見ながら考えましょう。 原文 この喫茶店のコー ...
事実を先に書く
すべての文章に含まれる内容は、「事実」と「感想」に大きく分かれます。 これらは、文章構成において優先して考えるべき要素となります。 なぜなら「事実」と「感想」の組み込み方しだいで、文章の読みやすさが変わってくるからです。 ...
長すぎる修飾を避ける
文章が長くなれば、読み手に負担をかけることになります。 書き手として特に気をつけたいのは、修飾するときです。 文のなかで長々と修飾してしまえば、読みづらい文章になってしまうのです。 原文 アメリカの ...
漢字が重複するときは要注意
ひとつの文のなかで、同じ漢字を2回以上使う場合があります。 同じ漢字を2回以上使うこと自体はなんら問題ありません。 しかしこれは、ミスを知らせるためのサインとなるのです。 原文 彼女は、他人のことを ...
適切な言葉づかいは文書によって変わる
書き言葉と話し言葉は、似て非なるものです。 どちらの言葉づかいが適切なのか、その判断に迷ったら書き言葉を使うことをおすすめします。 文章を書くのですから、当然ですね。 しかしプライベートなやりとりをはじめ、堅くな ...
早い段階で主旨を示す
文章の組み立てに問題があると、最後まで読まなければ意味が通じなくなることがあります。 そのような文章では、読み手に大きな負担をかけてしまいます。 原文 バーのカウンターに座っていると、突然「結婚生活 ...